

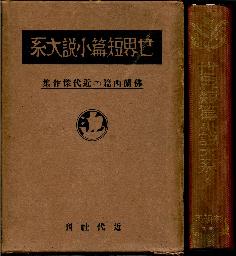
『パリを焼く』の中身は意外にも「パリで焼く」だった訳ですが、パリでペストゆーたら普通はデルテイユ。こっちだったらウェルズだオブライエンだチェンバーズだミドルトンだっ、てんでSFの人は基本文献として買っちゃう『世界短篇小説大系』に入っているので、たまに、なんじゃこりゃと読んでしまう人が・・・、いません?
さて、ジョゼフ・デルテイユ(Joseph Delteil,1894〜1978)というと、今やドライヤーの『裁かるるジャンヌ』の原作者としてかろうじて名を留めるのみかと。
で、柳下美恵伴奏の『裁かるるジャンヌ』上映を見に行ったら原作者扱いされとらんかったぞ。何、ドライヤー、デルテイユの映画化ということで企画を持ってこられたけど結局デルテイユ作品を蹴って改めて古文書を調べて脚本にしたんだって?
デルテイユはこの『ジャンヌダルク』で1925年のフェミナ賞を獲得しとるんだが、これにしたって「そこではエレエヌ・ヴァラレスコが講演をしていた。そして彼女はその議長投票で、デルテイユの「ジャンヌ・ダルク」にフェミナ賞を授与して、淑女たる名声を危うくしたばかりだった。」とキク・ヤマタに書かれちゃってます(<世界文学>第10号、1947年5月25日→後に『パリの作家たち』に収録)。
昭和6年刊行の白水社『新興仏蘭西文学』においてもボロクソ。「「ジャンヌ・ダルク」や「兵隊さん」を書いたジヨゼフ・デルテイユは、彼の本当の価値と全く不釣合な過当の名声を博してゐる。彼には率直なしほらしさと喧嘩好きの剽悍さがあるやうに思はれてゐるが、その率直さは嘘のもので、喧嘩好きの態度も作りものに過ぎない。彼には殆ど創意もなければ風格も全然ない。彼は不調和な雑色をやたらに塗りたててそれで窮地を脱しようとしてゐる。ところがさうした窮余の策が、一部の崇拝者には彼が恰も天才であるかのやうな錯覚を起こさせるのである」
なんか一瞬、かっちょいいと思われたもののすぐ化けの皮が剥がれて、あっという間に消えた作家みたいだが、ヘンリー・ミラーと文通したりして、それなりに細く長く活動していた模様。
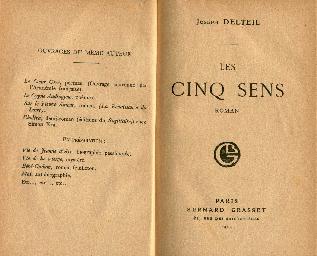 この「黒死病の巴里」は第二次大戦直後には改めて「ペストは巴里へ」として翻訳されて(山崎清訳、<世界文学>5号、1946年9月30日)たりするし、なんかのアンソロジーにでも収録されていそうなんだが、よくわからん。ともかく原作は何なんだと調べていると長編(独立した単行本として出ているので取り敢えず長編扱いしちゃうが、おそらく全訳しても300枚を切ると思われ、実質的には長めの中編か)Les cinq sens(1925)の第一章かよっ。
この「黒死病の巴里」は第二次大戦直後には改めて「ペストは巴里へ」として翻訳されて(山崎清訳、<世界文学>5号、1946年9月30日)たりするし、なんかのアンソロジーにでも収録されていそうなんだが、よくわからん。ともかく原作は何なんだと調べていると長編(独立した単行本として出ているので取り敢えず長編扱いしちゃうが、おそらく全訳しても300枚を切ると思われ、実質的には長めの中編か)Les cinq sens(1925)の第一章かよっ。
前述したキク・ヤマタの文章は「フランス作家印象記 その一」なんですが、実は、この書き出しが「今、日本でデルテイユの「五感」がほんやくされている。」となっとるんやが、これは山崎訳のことなの? それとも別に全訳をすすめていた人がいたのか。山崎清さん自体よくわからんのだが、有名な人なんやろか。
さて、物語は1925年、ナポレオンの命日である5月5日、パリの各所でペストとラベルの貼られた試験管が次々と見つかる。その多くは気づかれずに踏み割られていた。6日にはパリだけで2943人、7日には19172人。ペストに斃れる人の数は日に日に増え、13日には273544人を数える。『パリを焼く』とは違って、疫病の封じ込め作戦は展開されず地方にまで疫病はひろがっていく。
5月12日には医学統治権が設定され総裁にパストゥール研究所長のエレオノオル・プレッシイが任命される。そして、フランス大学の教授エリイエリイ博士もペスト大臣となった。
辻々に北極へ向かっての脱出行を勧める説教師が現れ、疫病が暑い亜細亜から来たものと断じ、黴菌に対抗するものとして氷を崇拝し北極を賛美するのであった。(終)
なんじゃそりゃ。こんな結末で納得したの? シュールレアリスム系の作家と目されてたので、シュールだねえ、ですまされとったんかっ。
どうみてもバイオテロもの見たいな冒頭だが。章立は以下の通り。
La Peste a Paris/Castelnaudary/Embarquement du monde/Paris/Monsieur le Maire/Elie-Elie/Amour, Amour/Le Festin de la Mort/Contagion/Boxes/Vive la Vie!/Londres/Dualite/Mouche/Arithmetique/L'Iceberg/Supplice
これだけだと、どんなストーリーかさっぱりわからん。
諸般の事情によりほとんど時間がとれんかったが、時間いっぱい辞書を引き引き最初の方を読んでみたけどよくわからなかったよ。はっはっはっ。(どうもエレオノオルの指揮の下、北極への一大脱出プログラムが推進されとるような気がする)
その後のデルテイユの日本での紹介ぶりを、ざっと調べて見ると、大野俊一による訳が昭和4年に2本。「巴里の猫」(<創作月刊>2巻1号、1929年1月1日、103〜106頁)、「巴里の橋の下で」(<創作月刊>2巻3号、1929年3月1日、126〜128頁)。いずれも、散文詩みたいな掌編である。前者はAllo! Paris!から訳したとあるので、おそらく後者もそこから訳されているものではないかと思われる。これって、ロベール・ドローネーが挿絵をつけた限定版ということで値がついているやつか。
実業之日本社が昭和15年に刊行を開始した仏蘭西文学賞叢書の刊行予定書目には当初から杉捷夫訳の『ジャーヌ・ダーク』(ヂャーヌ・ダルクとも)が出ていたが、その実現の前に叢書の刊行は途絶えてしまう。戦後『世界の人間像6』角川書店、1961年12月30日に、ようやく花輪光訳「ジャンヌ・ダルク」が収録され、邦訳が成った。二段組とはいえ百頁を切っているので抄訳かと思わされるが、ざっと突き合わせた限りでは完訳のようである。
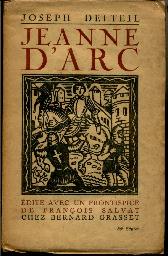
本国では、細々とながら再評価する人が現れていないようでもないので、フランス文学な人に、ぜひ、改めて読んであげていただきたい、と提案して今回はおしまい。
矢野目源一訳「黒死病の巴里」『世界短篇小説大系 仏蘭西篇(下)』近代社、大正14年8月25日、751〜766頁