


|
続・サンタロガ・バリア (第118回) |
5年ぶりくらいに連休中に休みが取れたので、物好きにも車で遠出する(助手席で寝てるだけだけど)。久しぶりに高速道路を走る他の車を(抜かれつつ)見ながら、いわゆる外車(ランボルギーニや黄色いポルシェは別として)も地味に見えるようになったなあと思った。あれは今という時代のデザインなんだろうな。
ケンペの「マイスタージンガー」は未だに聴き終わらず。解説書を読んでいるとこのCDは、状態のよいレコードから起こしたと書いてあった。それでアナログ盤特有のノイズが入るのかと納得。スクラッチやワウ・フラッターといったレコード再生では避けられない雑音が時々はいる。それはあまり気にならないけれど、オリジナルテープ起こしのCDも聴いてみたい。ロックの方ではマーズ・ヴォルタ「Noctourniquet」を聴いている。洋楽ロックもほとんど聴かなくなったけれど、このバンドは出る度に買っている。ゼップやクリムゾンが持っていたプログレな臭いがなんとなく感じられて、好きなんだろう。しかし、ヴォリュームを上げて聴くと非常にウルさい。
ボサ・ノヴァが聴きたいと思いジョアン・ジルベルトの60年頃のアルバム3枚セットを聴いてみた。ビックリしたのが1曲あたりの演奏時間の短いこと。有名曲でも1分20秒とかで終わってしまうものがあり、リフレイン込みでも2分前後で、12曲で30分もない。ジャズやヴォーカルものそれにYouTubeでのジルベルト自身の歌も3分以上かけて歌われることが多いため、オリジナルはこんなにあっさりと終わるのかと衝撃を受けた。考えてみれば、当時のブラジルではまだSP盤の収録時間で曲作りをしていたのかもしれない。まさに一世を風靡しようという時代のボサ・ノヴァは、ジルベルトの歌唱とジョビンの作編曲の斬新さも含めて、一種野蛮なパワーが溢れていたのだった。
 |
 |
 |
ちょっと地獄編を読み始めてしまったので天国編まで行ってしまった河出文庫版ダンテ『神曲』。河出の世界文学全集版(グリーン・シリーズだったっけ)も岩波文庫版も集英社の寿岳文章訳版も昔から実家にあったけれど、読む気はまったく起きなかった。のに、平川祐弘訳の文庫版を読み出したら最後まで続いたのは何故なんだろう。
それはともかく、地獄編が一番面白く天国編が一番退屈なのは評判通りで、天国が退屈なところだという話はダンテの所為じゃないかと疑わざるを得ない。その証拠にギュスターヴ・ドレといえども天国の描きようがなく挿絵が全然面白くない。面白いのはダンテの悪口で、まあ自分の嫌いな奴をひどい目に遭わせてやりたい放題。天国に行ってまで悪口はとどまるところを知らないんだからあきれる。ダンテはもともと「喜劇」という題を付けたらしいが、それは自分がフィクションに任せて何をやっているのかを自覚していたということだろう。地獄編の最後なんかまさにコミックだもんねえ。それにしてもベアトリーチェがただの説教マシーンで、なんでダンテがこんな女に惚れていたのかサッパリ判らない。だいたい人妻に懸想していていいのかダンテ君。
 昨年出たSFがらみのアメリカ評論その2は、H・ブルース・フランクリン『最終兵器の夢』(抄訳版)。こちらは18世紀の武器開発業者としてのロバート・フルトンから始まって21世紀に続く核兵器の悪夢までを、超兵器の登場するアメリカSFの系譜をたどりつつ軍事ヒステリーの歴史として紹介したもの。前半に出てくるSFは1世紀以上も前の作品から第2次世界大戦前までの、日本ではほとんど知られてないものが数多く採りあげられていてるし、有名SFは核戦争ものばかりでSFファンの視点からは物足りないけれど、基本的にはテーマが単純なこともあって、読み物としてはフレドリック・ジェイムソンよりずっと読みやすい。スタージョンの「雷(鳴)と薔薇」が高く評価されているのは、この本の趣旨からいって当然とはいえ嬉しい。SFマガジンでも紹介された「スター・ウォーズ計画」の章が省略されているのが残念だ。
昨年出たSFがらみのアメリカ評論その2は、H・ブルース・フランクリン『最終兵器の夢』(抄訳版)。こちらは18世紀の武器開発業者としてのロバート・フルトンから始まって21世紀に続く核兵器の悪夢までを、超兵器の登場するアメリカSFの系譜をたどりつつ軍事ヒステリーの歴史として紹介したもの。前半に出てくるSFは1世紀以上も前の作品から第2次世界大戦前までの、日本ではほとんど知られてないものが数多く採りあげられていてるし、有名SFは核戦争ものばかりでSFファンの視点からは物足りないけれど、基本的にはテーマが単純なこともあって、読み物としてはフレドリック・ジェイムソンよりずっと読みやすい。スタージョンの「雷(鳴)と薔薇」が高く評価されているのは、この本の趣旨からいって当然とはいえ嬉しい。SFマガジンでも紹介された「スター・ウォーズ計画」の章が省略されているのが残念だ。
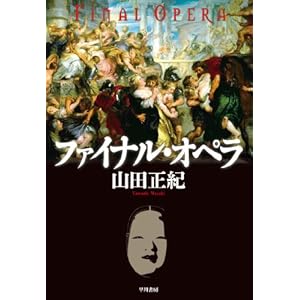 山田正紀『ファイナル・オペラ』は『ミステリ・オペラ』に始まったオペラ三部作もしくは検閲図書館シリーズの最終作。舞台は昭和20年を現在とした戦時下の八王子。お題は、神社に伝えられた秘能。14年前の上演時に起こった舞台上の殺人事件の謎解きを中心として、空襲が近づく昭和20年のその時に向かって再演の話が進む。話のノリが悪いのは、なにも語り手が最初から私を信頼するなといっている所為だけではないだろう。記憶では前2作はとても面白く読めたように思うのだが、この作品は作者の自己確認みたいな叙述が多くてなかなか前に進めないのだ。それはエンターテインメントをメタフィクションで覆うことで何かを生み出そうとしているように見えるが、成功しているとは言い難い。人工的/芸術的であることとテーマを担うキャラクターたちの言葉が乖離し、祈りはあまりにもテクニカルであることで届かない。そんな感じのする力作だ。
山田正紀『ファイナル・オペラ』は『ミステリ・オペラ』に始まったオペラ三部作もしくは検閲図書館シリーズの最終作。舞台は昭和20年を現在とした戦時下の八王子。お題は、神社に伝えられた秘能。14年前の上演時に起こった舞台上の殺人事件の謎解きを中心として、空襲が近づく昭和20年のその時に向かって再演の話が進む。話のノリが悪いのは、なにも語り手が最初から私を信頼するなといっている所為だけではないだろう。記憶では前2作はとても面白く読めたように思うのだが、この作品は作者の自己確認みたいな叙述が多くてなかなか前に進めないのだ。それはエンターテインメントをメタフィクションで覆うことで何かを生み出そうとしているように見えるが、成功しているとは言い難い。人工的/芸術的であることとテーマを担うキャラクターたちの言葉が乖離し、祈りはあまりにもテクニカルであることで届かない。そんな感じのする力作だ。
 山田正紀に手こずってる間に、ちょっと浮気したら1時間で読み終わった(祝叙勲?)萩尾望都『マンガのあなた*SFのわたし-萩尾望都対談集1970年代編−』は、やはり懐かしい空気が感じられてちょっと胸が温かくなる1冊。手元にはもはや1冊も置いてない萩尾望都だが、リアルタイムで読んでいた光瀬やブラッドベリの画面はあの時代を思い出させて、最近は滅多に感じない感傷を呼び起こす。最後の羽海野チカとの対談と較べれば昔の対談や鼎談が如何にのんびりしたものだったかがよく分かる。
山田正紀に手こずってる間に、ちょっと浮気したら1時間で読み終わった(祝叙勲?)萩尾望都『マンガのあなた*SFのわたし-萩尾望都対談集1970年代編−』は、やはり懐かしい空気が感じられてちょっと胸が温かくなる1冊。手元にはもはや1冊も置いてない萩尾望都だが、リアルタイムで読んでいた光瀬やブラッドベリの画面はあの時代を思い出させて、最近は滅多に感じない感傷を呼び起こす。最後の羽海野チカとの対談と較べれば昔の対談や鼎談が如何にのんびりしたものだったかがよく分かる。
 ちゃんと毎年出るらしい創元SF短編賞アンソロジー、大森望/日下三蔵編『原色の想像力2』は、どれも読ませるけれど、ちょっとだけエッジが足りない作品が多い。面白さではどれも十分面白いし、関西弁のネエチャン/オバハンが出てくる「What We Want」なんかは好きかも。でもSFで何をしたいのかというところがまだ物足りない。その点、酉島伝法「洞(うつお)の街」は抜群のイメージ構築力で世界を作り上げていて圧巻。ストーリーはイメージほど斬新ではないけれど、それでもここしばらく読んだ短編ではベストに入る出来だろう。『NOVA』にもこういうのが1本欲しいなあ。
ちゃんと毎年出るらしい創元SF短編賞アンソロジー、大森望/日下三蔵編『原色の想像力2』は、どれも読ませるけれど、ちょっとだけエッジが足りない作品が多い。面白さではどれも十分面白いし、関西弁のネエチャン/オバハンが出てくる「What We Want」なんかは好きかも。でもSFで何をしたいのかというところがまだ物足りない。その点、酉島伝法「洞(うつお)の街」は抜群のイメージ構築力で世界を作り上げていて圧巻。ストーリーはイメージほど斬新ではないけれど、それでもここしばらく読んだ短編ではベストに入る出来だろう。『NOVA』にもこういうのが1本欲しいなあ。
 オビに「どちらかというとわかりやすい最新作品集」と書かれてしまう円城塔『バナナ剥きには最適の日々』は、内容はともかく読みやすい字面であることは確かだ。ま、CDの歌詞カードと同じサイズで印刷された「equal」は別として。
オビに「どちらかというとわかりやすい最新作品集」と書かれてしまう円城塔『バナナ剥きには最適の日々』は、内容はともかく読みやすい字面であることは確かだ。ま、CDの歌詞カードと同じサイズで印刷された「equal」は別として。
表題作が一番愉しく読めるのは当然だけれど、論理の使い回しと小説的アイデアと倫理が渾然となった感触がその他の作品からは窺える。それは「信じる」ことと「論理学」的な思考の両方にかかり、書くことが伝えることの前提であるという確信が倫理を形作る(それがどう受け取られるかは違う世界の問題か)。「equal」が目次の真ん中に置かれているのは明らかに意図的なんだろう。