|
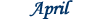
《サザーン・リーチ》を書いたジェフ・ヴァンダミアの本職(アンソロジイなどの編集者)でもある、スチームパンクまとめムック本。スチームパンク本では、昨年2月にブライアン・J・ロブの『ヴィジュアル大全スチームパンク』(2012)が出ているので、内容的には被る部分もある。日本でのブームの度合いは不詳だが、フィクションの世界を抜け出し、ファッションや生活スタイルにまで浸透したという点で、サイバーパンク以来の社会的ブームとなった。アメリカでは、ニューヨークタイムズの記事が書かれた2008年あたりをピークとするようだ。
さて、本書はスチームパンクの起源を、まずヴェルヌから説き起こす。登場する19世紀ベースのハードウェアで、リアリティを追求したヴェルヌは、今日なら近未来サスペンス小説と呼ばれるようなスタンスだった。ヴェルヌはウェルズの小説には科学的な裏付けがないと批判する。ただ、そのリアリティは今読むと架空のもの、実現不可能なものでしかなく、余計にスチームパンク的となる。
ただし、そこからスチームパンクが始まるとすると、それはSFそのものと重なってしまう。最初のスチームパンクといえるものは、ムアコックの未訳シリーズ《Nomads
of the
Time》(1971-81)、もっとも影響を与えた作品はギブスン&スターリング『ディファレンス・エンジン』(1990)だ。この用語を考えたのは、20代だったジーター『悪魔の機械』(1987)、パワーズ『アヌビスの門』(1983)、ブレイロックらである。
その後、小説としてのスチームパンクはプリースト『ボーンシェイカー』(2009)、キャリガー《英国パラソル奇譚》(2009-)、エカテリーナ・セディア(短篇のみ翻訳)まで10年が開く。その間に、フィクション以外のヴィクトリア風ファッションなどが注目されるようになる。キャリガーは、ムアコックよりファッションの影響を受けたという。同時期に『リヴァイアサン』(2009)を書いたウェスターフェルドは、スチームパンク愛好家は、コスプレをする場合でも、特定のキャラクターではなく時代そのものに興味を示すと指摘する。
ヴィジュアル、造形の世界ではもっと多様な作品が生まれる。デザイナーでもあるグレッグ・ブロードモア、マイク・ミニョーラ、フィル&カヤ・フォグリオ、アラン・ムーア&ケビン・オニール、ブライアン・タルボットらによるコミック。さらに、1983年から作られ始めた巨大なテーマパークのようなフォーエヴァートロン、ギブスンの短編「ガーンズバック連続体」に触発されたレイガン・ゴシック・ロケットシップ(飛べるロケットではない)、メイカーたちの集まるスチームパンク・ワークショップで代表的なデータマンサー、キネティック・スチーム・ワークス(KSW)など、これらは作っているものを見れば、何を目的にしているかがある程度理解できる。フアッションに関しては、上記ニューヨークタイムス記事に類することが、日本でも見られるようになった。
本書の場合、日本の事情についてかなり詳しい説明がある。ヴェルヌの影響を受けた押川春浪『海底軍艦』(1900)、裏返しの帝国主義小説でもある巌垣月洲『西征快心篇』(1855)などから始まって、代表的なスチームパンクは宮崎駿『天空の城ラピュタ』(1986)、『ハウルの動く城』(2004)とする。また、ヴェルヌ的な影響を脱したスチームパンク映画として、(なぜか)紀里谷和明の『CASSHERN』(2004)を絶賛している。そういう見方をすれば、確かに評価できるのかもしれない。
スチームパンクをメイカーの立場から取り上げていることから分かるように、本書では量産品ではない手造を志向する技術の象徴としてスチームパンクを扱っている。蒸気革命が帝国主義そのものだった、19世紀の社会や政治体制は過去のものとなった。新しい蒸気の世紀は、画一的な20世紀を超える存在として、欧米以外の地域を含め、中国から南米、インド、アジアまで世界的な広がりを見せている。 |
|