
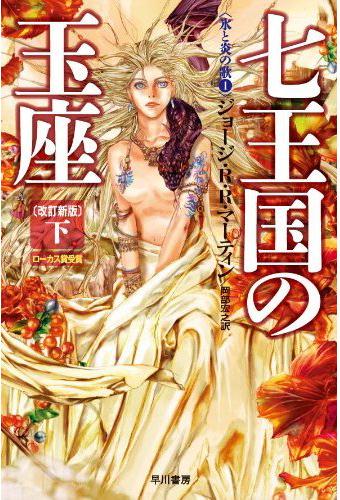
 |
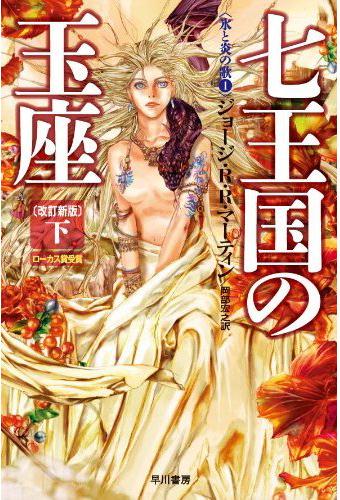 |
ジョージ・R・R・マーティン/岡部宏之訳
『七王国の玉座 [改訂新版] 氷と炎の歌1』 解説
大野万紀
ハヤカワ文庫
2012年3月25日発行
(株)早川書房
A GAME OF THRONES by George R.R. Martin (1996))
ISBN978-4-15-011844 C0197 ISBN978-4-15-011845 C0197
本書は〈氷と炎の歌〉第一部『七王国の玉座』六年ぶりの再文庫化です。
二〇〇六年に出版された文庫版は全五巻でしたが、今回はハードカバーと同じく、上下巻。それと、もう一つ大きな違いがあります。
本書で初めて〈氷と炎の歌〉シリーズを手にされる方、また第四部『乱鴉の饗宴』のみ読んだという方には関係ありませんが、これまで第一部から第三部までを読まれた方は、あれっと思われるかも知れません。これは第四部で日本語版の訳者が岡部宏之さんから酒井昭伸さんに変わり、それに伴って用語や人名の翻訳に変更があったためです。
本書の訳者は岡部さんで変わらず、訳文も当初のままで変わっていませんが、用語や人名の一部は岡部さんの了承のもと、第四部に合わせて統一されています。例えば冒頭に登場する〈冥夜の守人(ナイツ・ウォッチ)〉は以前は〈夜警団(ナイツウォッチ)〉と訳されていました。
このあたりのいきさつは、第四部『乱鴉の饗宴』の訳者あとがきで詳細に説明されていますが、一言でいえば、作者の思いにできるだけ近づけ、世界観を明確にするため、そして人名など固有名詞についても、音の響きを重視する作者の意向を尊重し、朗読を元に原文の発音に近い形にするという訳者の方針が示されています。
しかし、これは大きな反響を呼びました。何より、人名までが変わってしまったことに、これまでこのシリーズを楽しんできた読者の戸惑いがありました。確かに、大河ドラマの組織や登場人物の名前が途中から変わったらびっくりしますよね。
でも、これはある意味グローバル化した現代ではやむを得ないことだと思います。ロナルド・リーガンがある日突然レーガン大統領になったりするようなものですね。国内だけで楽しんでいるぶんには問題なくても、本書はアメリカでテレビドラマ化もされ、インターネットでリアルタイムに情報のやりとりもされているわけです。翻訳もそういうことまで意識しないといけない時代になったのだと思います。
とにかく、これでシリーズ全体の用語・人名が統一されたわけで、これから本シリーズを読もうという方、また第四部を読んでこれまでの作品を読みたいと思われた方には、この文庫から読んでいけば違和感なく楽しめるかと思います。
ちょっと前置きが長くなってしまいましたが、あらためて。本書はジョージ・R・R・マーティンの現在第五部まで刊行されている大河ファンタジイ〈氷と炎の歌〉シリーズの第一部、『七王国の玉座』A Game of Thrones (1996)の、用語を新訳に統一した改訂版です。第二部以降もこれから順次同様に用語を統一して文庫化されていきます。本書はシリーズの全体から見ればまだほんのプロローグ。物語はこれからどんどん波瀾万丈に、壮大に、複雑に、そして怪奇になっていくのです。
とにかく長大で複雑な物語なので、まずは簡単な見取り図を頭に入れておきましょう。各章ごとに視点人物が変わり、いくつもの物語が並行して進んでいくので、うっかりすると迷子になってしまいます。いや、まったく予備知識なく、新たな展開に驚きながら読み進むというのも、このような物語の楽しみの一つかもしれませんが。
〈七王国〉とは、中世イギリスを思わせるこの架空世界の島国の名前であり、かつてはその名の通り七つの王国に分かれていました。三百年ほど前に統一され、今は一つの王国となっています。しかし、この国にまた分裂と戦乱の嵐が巻き起ころうとしているのです。本書の段階ではまだその萌芽となる怪しげな動きが語られているのみですが、この後物語は怒濤の展開を見せ、本書に登場する人々はみな、大人も子供もそして狼たちも、その嵐に巻き込まれていきます。
本書の主要な舞台は、北部地方。エダード・スターク公の領有する、厳しい冬の世界です。ちなみにこの世界ではどういうわけかもう十数年も夏が続き、人々の間に来るべき冬への不安が広がっているのです。本書の冒頭では、北部地方のさらに北に広がる野生人の世界と、そこで起こっている不気味な異変について語られます。そこには〈壁〉と呼ばれる長城が築かれ、〈冥夜の守人(ナイツ・ウオッチ)〉が昼夜警備を続けて、〈異形(ジ・アザー)〉や大狼(ダイアウルフ)といった人知を越えた存在から王国を守っているのですが、その地で死者が生き返るといった奇怪な事件が起こっているのです。もっとも、この話は今のところ物語のメイン・テーマにはからんできません。しかし〈氷と炎の歌〉の全体の背景として、底知れない不安な通奏低音を響かせているのです。
一方、物語のメイン・テーマとしては、そのスターク家と、現国王の王妃の実家であるラニスター家との、二大勢力の抗争が描かれていきます。本書ではまだその発端である、国王の補佐役〈王の手〉の死にまつわる陰謀がほのめかされているだけなのですが、やがて舞台が王都(キングズ・ランディング)に移り、権謀術数の数々とそれに巻き込まれる人々の姿が描かれることになります。本書がイギリスの薔薇戦争をモチーフにしているとは作者本人も語っていることですが、このあたりになると(そしてその後の王国を分裂させる激しい戦争の物語となると)ファンタジイの要素は背後に隠れ、ほとんど重厚な歴史小説の趣を呈してきます。宮廷の陰謀と英雄たちの戦い、その中で翻弄されつつも毅然と生きる女性や子供たちの姿など、まさに戦国絵巻を見るようだといっても過言ではないでしょう。
実際、主要な登場人物を戦国時代の武将や姫君に当てはめて読むのも面白いかも知れません。もちろんぴったりと合致させるわけにはいかないのですが、信長や光秀、秀吉や淀君といった人々の、ある一面を思わせるような個性が、本書の登場人物たちにも見て取ることができます。現実の戦国時代やヨーロッパ中世と同じく、悪意ある残酷さや権力欲と同時に武士道や騎士道につながる高潔さや名誉の重視、そして家族への愛情も共にあって、単純な善玉悪玉ではない、現実を生きている人間ならではの複雑さをもった人々の物語となっているのです。印象に残るのは悪意からにしろ善意からにしろ、邪悪さや高潔さから発したものにしろ、権力者たちのそうした人間性が個々の人々にとっては残酷な運命に直結していくという時代の重さ、そしてそういう社会の中でもくじけず生きていく人々の力強さでしょう。このことが、本書をよくあるロールプレイングゲーム的な異世界ファンタジイとはひと味もふた味も異なる、まさに大河歴史小説的な読後感のあるものとしているのです。
本書ではもう一つ、スターク公や現国王によって滅ぼされた、かつての王家、ドラゴンの血をひくというターガリエン家の最後の王女(プリンセス)、十三歳にして海の向こうの騎馬民族の王と結婚することになったデナーリスの物語も語られます。こちらの物語も、〈壁〉の向こうの物語と同様、まだまだ本筋にはからんでこないのですが、本書がまぎれもなくファンタジイ、あるいは作者のいう”イマジネイティブ・フィクション”であることを示す重要なパートとなっています。
本書の視点人物としては、先に挙げたエダード・スタークの他に、エダードの奥方であるキャトリン、エダードとキャトリンの幼い息子であるブラン、まるで男の子のように活発な次女のアリア、エダードの私生児であり〈冥夜の守人(ナイツ・ウオッチ)〉に入ることになるジョンといった、スターク家にまつわる人々と、数奇な運命をたどるターガリエン王家の末裔デナーリス、そしてラニスター家の次男、王妃の弟でありながら発育不全の一寸法師で皮肉屋のティリオンが登場します。いずれも魅力的な個性の持ち主ですが、中でやはり一番面白いといえるのは、本書の世界での様々な対立の枠組みを超越した、〈小鬼(インプ)〉と呼ばれるティリオンでしょう。彼は今のところこの物語の中で唯一といっていい、自由な視点で大きな物語を語ることのできる、開かれた知性を持った人物です。その魅力がより発揮されるのはおそらく第二部からなのですが、本書でも十分その雰囲気を味わうことができるでしょう。
さて、ジョージ・R・R・マーティンといえば、ぼくら古い海外SFのファンにとっては、七〇年代から活躍しているアメリカのSF作家であり、ヒューゴー賞やネビュラ賞、ローカス賞の常連であるという印象があります。実際、七四年の「ライアへの賛歌」からヒューゴー賞四回、ネビュラ賞一回、候補作やローカス賞にいたっては数知れずという華々しい受賞歴の持ち主です。また純粋なSFだけでなく、ホラーやファンタジイとSFとを融合させたような、まさに”イマジネイティブ・フィクション”を書く作家だといえるでしょう。
七〇年代のマーティンは、いわゆるLDGの代表選手としても知られていました。LDGといっても何のことかわからないでしょうが、これはレイバー・デイ・グループの略で、レイバー・デイ(労働者の日。九月の第一月曜日)を含む週に開かれる世界SF大会で、ヒューゴー賞の常連となっていた七〇年代の若手作家たちを示す言葉です。マーティンの他にはジョン・ヴァーリイやマイクル・ビショップ、ヴォンダ・N・マッキンタイアなどが含まれていました。彼らはその前の世代に属するトーマス・M・ディッシュから、芸術性より仲間受けを優先しているなどと批判されましたが、マーティンはそれに反論して、ディッシュの批判には根拠がないが、LDGと名付けられる同世代の作家グループは存在し、「自分たちの世代は宇宙時代の最初の子供であり、その片足はハイ・テクノロジーとハイ・アドベンチャーと楽天主義の陣営にある。その一方で自分たちはベトナム戦争とフラワーチルドレンとアナーキズムと幻滅と懐疑の世代でもある。そして六〇年代のこの二つの陣営のジンテーゼこそ自分たちの目指すものなのだ」と主張しました。彼の次の言葉は、今でもぼくの心に残っています。
「LDGが心の底でおこなおうとしているのは、まさにこれだと思う。良きトラディッショナルSFの持つカラーと迫力と無意識の力を、ニュー・ウェーヴの持つ文学的関心と結びつけること、詩人とロケット屋を交わらせ、二つの文化に橋をかけることだ」
彼の作品は、まさにこのようなものでした。そして、そういえば本書にもまた、リアルで骨太な大河歴史小説の枠組みの裏に、ファンタジイというよりもむしろSF的なフレーバーがあるように感じられます。それは決してあからさまなものではなく、本当に微妙なものなのですが、それこそ”良きトラディッショナルSFの持つ無意識の力”を感じさせるものなのです。
SF作家としてのマーティンについて興味を持たれたならば、『タフの方舟』シリーズを読んでみることをお勧めします。宇宙一あこぎな商人タフが活躍するこの連作宇宙SFには、溢れるユーモアや息もつかせぬ冒険の背後に、やはり単純な二元論では割り切れないリアルな問題意識があります。環境問題への苦い認識など、声高ではないが確かにある時代を生きてきた作家としての主張が感じられるのです。
〈氷と炎の歌〉シリーズは原著の第五部が二〇一一年に出版されたばかり。サイトには今のところ第七部までの出版予告があがっています。いやあ、大河小説が終わらずにまだまだ続くのはある意味結構なことですが、登場人物たちの運命がどうなるのか、はらはらしながら待ち続けるのも辛い話で、なんとか間をおかずに出してほしいものです。
最後に、『七王国の玉座』のドラマ化について。アメリカのケーブルテレビ局HBOで超大作として二〇一一年にドラマ化された本作は、第一シーズンが放送を終わり、現在第二シーズンの放送中です。『ロード・オブ・ザ・リング』でボロミアを演じたショーン・ビーンがエダード・スターク公を主演し、そして二〇一一年のエミー賞ではティリオン役のピーター・ディンクリッジが助演男優賞を受賞しました。とても好評なのですが、残念なことに今のところ日本では放送されていません。YouTubeで一部は公開されていますので、検索してみてください。また、このテレビドラマ版はゲーム化もされ、PS3やXBOXで近日中に発売とのことです。
2012年2月