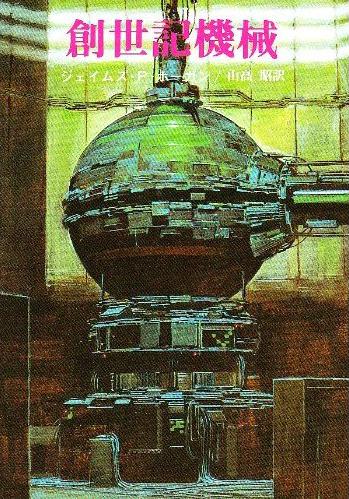
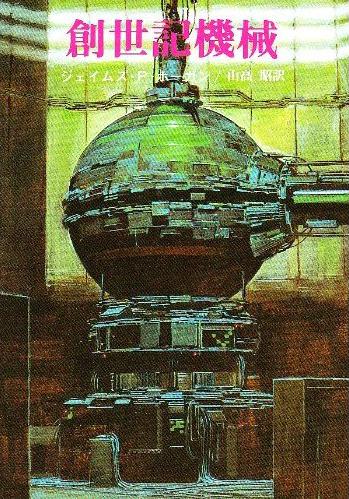
ジェイムズ・P・ホーガン/山高昭訳
『創世記機械』 解説
大野万紀
創元推理文庫
1981年10月30日発行
(株)東京創元社
The Genesis Machine by James P. Hogan (1978)
本書は『星を継ぐもの』『ガニメデの優しい巨人』につづく、J・P・ホーガンの邦訳三冊目の長編だが、シリーズとなっている前二作とはいささか趣を異にする、独立した作品である。
SFがサイエンス・フィクションの略であるとは、もうずいぶん昔から断言できなくなってきた。にもかかわらず、サイエンス・フィクションだというSFがある。昔風な空想科学小説という呼び名がぴったりする一群である。〝ハードSF″という呼び名にはいろいろ議論があって、正確にはどうかわからないが、普通の使い方であればこれをハードSFと呼んでもかまわないだろう。
本書はそういうSFの一集合{セット}の中でもさらに極端な部分集合{サブセット}に属する、〝発明・発見テーマ″の作品である。これはかつては非常に繁栄したが、現代ではほぼ絶滅したと信じられている、あの偉大な古代種族の直系の子孫なのだ。短編では細々と生き残っていた。また、その血は他の進化した種族の中にも確かに受け継がれてはいたのだが、まさかこれほど堂々と復活するとは思っていなかった。よくぞがんばったという感じである。
ヒューゴー賞の名を今に残すヒューゴー・ガーンズバックは、この〝発明・発見″の物語こそをSFと(正確にはサイエンティフィクションと)命名した。彼の創刊した世界最初のSF雑誌<アメージング>の第一号で、彼は「科学的なファクトと予言的なビジョンが混じり合った、魅力的なロマンス」をサイエンティフィクションと名付け、それは「常にためになるものであり、知識を口あたりのよい形にして供給するものだ」といっている。実際には、必ずしもこのような科学啓蒙的、予言的な作品が主流となったわけではない。しかし、今世紀初めの科学・技術革命の中で、SFはまず第一に、未来の新発明を予見しようとしたのである。
本書は、天才科学者のただ一つの新発見とその科学的・技術的発展にほとんどそのエネルギーのすべてを費やして書かれている点で、「ためになる」かどうかは別としても、このガーンズバック的SFの定義に合致している。もちろん、現代のSFであるから、科学者の社会との関わり方とか、そのモラル的な側面にも重点が置かれている。だがしかし、それは現代においてかの発明・発見物語を復活しようとするとき、必然的に生じる、避けられない問題であるともいえるのだ。この点に言及がなかったとしたら、おそらく読むに耐えないものとなっていただろう。だが本書の本当のテーマは、あくまでも〝新発見の科学理論とその応用″そのものにあるのだ。
ホーガンが創作した新発見の理論は、一種の統一場理論で、その核心は、重力場をも含めて記述したところにある。その重力の考え方はかなりユニークなもので、実際の科学理論にこれにヒントを与えたようなものがあるのかどうか、筆者は知らない。おそらく数学的・理論的根拠は何もない架空のものにすぎないのだろう(しかし多次元の空間によって重力場をも幾何学化する試みは実際になされており、たとえば十六次元の時空を考える理論がある)。重要なのは、この架空理論ひとつから、後はわりあい自然なスペキュレーションによって、まるで魔法のように意表をつく成果が次々と現われてくることだ。現代科学の常識に反するビッグ・バン理論の否定まで、当然の帰結として出てくるのだから、まったく驚かされる。
これを擬似科学にすぎないといって退けることはたやすい。まるで科学解説書のような記述があちこちに見られるが、根本の理論が創作なのだから、すべて意味のないものではある。しかしそれが嘘だとわかっていても、宇宙の謎が目の前で解明されるのを見るとき、センス・オブ・ワンダーを感じないSFファンがいるだろうか。おまけに現代の最先端の科学理論は難解で、しろうとの目にはそれが正しいのかどうかわからなくなっている。わかるのは、それが公認されたものかどうかということだけなのだ。だとしたら、知的カタルシスを与えてくれるアイデアが、実際は未公認な現実の仮説であっても、作家が考えた架空のものであっても、どれほどの違いがあるというのか。もちろんSFと現実を混同してはならないが、未知の世界を切り開いていく時に感じる感動は、現実の科学と変わらないはずのものなのだ。
これこそ〝発明・発見テーマ″が、SFのメイン・テーマからは外れたものの、幾多の名作の中でサブ・テーマとして生き続けてきた理由でもある。
とはいえ、現代のように科学が複雑化し、社会との関係も単純でなくなった時代に、かつてのスーパー科学者たちが住みにくくなったことは確かだ。科学者も組織の一員にすぎず、自宅の裏庭で宇宙船をつくるなどということはできなくなった。そう信じられてきた。
また、事実そうである。本書でも、科学者と組織との葛藤が大きなテーマになっている。にもかかわらず、とりわけ七〇年代の末あたりから、新しい時代が始まろうとしているかのように思える。再び科学が個人の手に届く時代。あるいはそういう方向性が常に求められる時代。裏庭で作った熱気球やハンググライダーで人々が空を飛び、能力的にはかつての大型コンピュータに匹敵するコンピュータをマイコン少年が手づくりする時代。本書の背景には、そういう新しい科学の時代である現代が反映しているのだ。おそらく十数年前なら、決して書かれなかった作品だといえるだろう。〝発明・発見テーマ″がこのような形で復活し得た理由はきっとそのあたりにあると思っていいだろう。
それにしても昔は簡単だった。リチャード・シートンやリチャード・アーコットといったかつてのSFのスーパー科学者たちは、読者を煙に巻くのに、これほどこみ入った理論を必要としなかった。<Ⅹ金属>で十分だった。今では、同じ〝スペオペ効果″を実現するのに、これほどの書き込みが必要なのである。そして、それがあまり違和感なく読めるということは、われわれの住んでいる現実そのものが、かつてのSF世界としだいに接近していることを示しているのではないだろうか。
ともあれ、本書は、架空ではあるが大変に現代物理学的なリアリティのある理論を基に、そこからあの昔なつかしい超発明、超兵器を導き出すスーパー科学者の物語である。過去の同僚たちと違い、彼には組織と政治の中にいる由の、悩みや苦しみがある。しかし、本質的には単なる発明・発見SFであるということが、積極的な利点となって、本書を壮快な読み物としているのだ。そこには純粋な発見の喜び「ユーレカ」がある。ハードSFが、難しい{ハード}SFだとお思いの読者には、ひょっとしたら本書の科学解説的部分は読みやすいといえないかもしれない。飛ばして読んでもさしつかえないだろう。だが、その部分に本書のエッセンスがあることを忘れないでいただきたい。別に理解する必要はないのだ。何だかわからないが、一所懸命考えているのだな、で十分。だまされる喜びを味わってほしいものだ。そうしてこそ、あの超兵器〝創世記機械″の作動する際の、胸のすくようなスペクタクルが、心から楽しめるというものだ。
作者、J・P・ホーガンについては、『星を継ぐもの』の解説に詳しい。最近聞いた話では、日本での評判が大変いいのに、ずいぶん感謝し、喜んでいるとのことだ。さすがは技術大国、ニッポンというところだろうか。
1981年9月